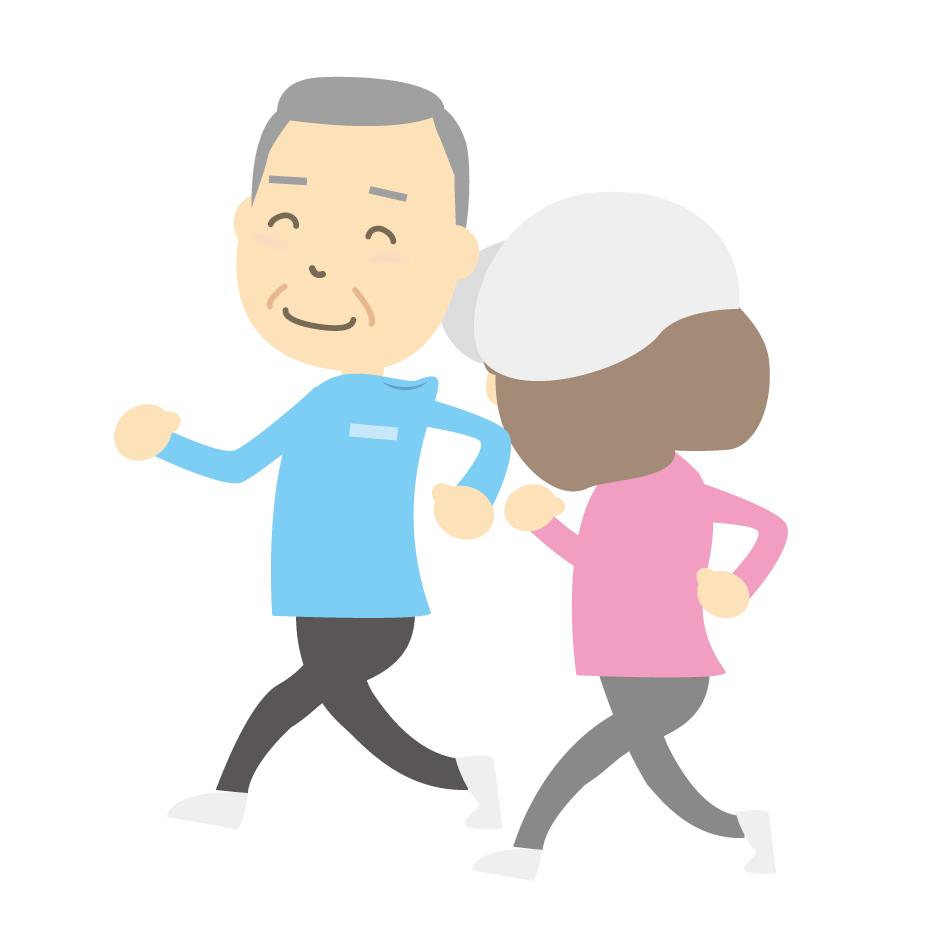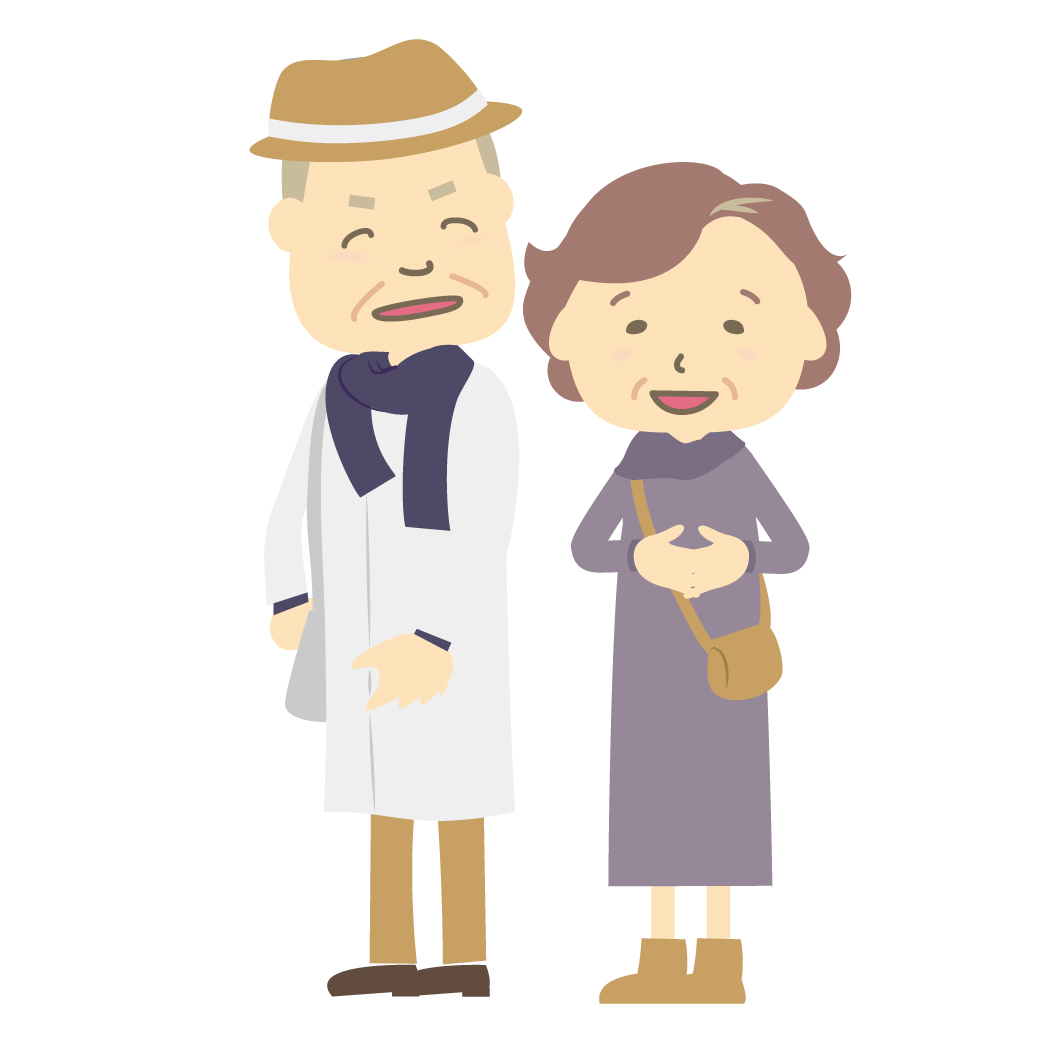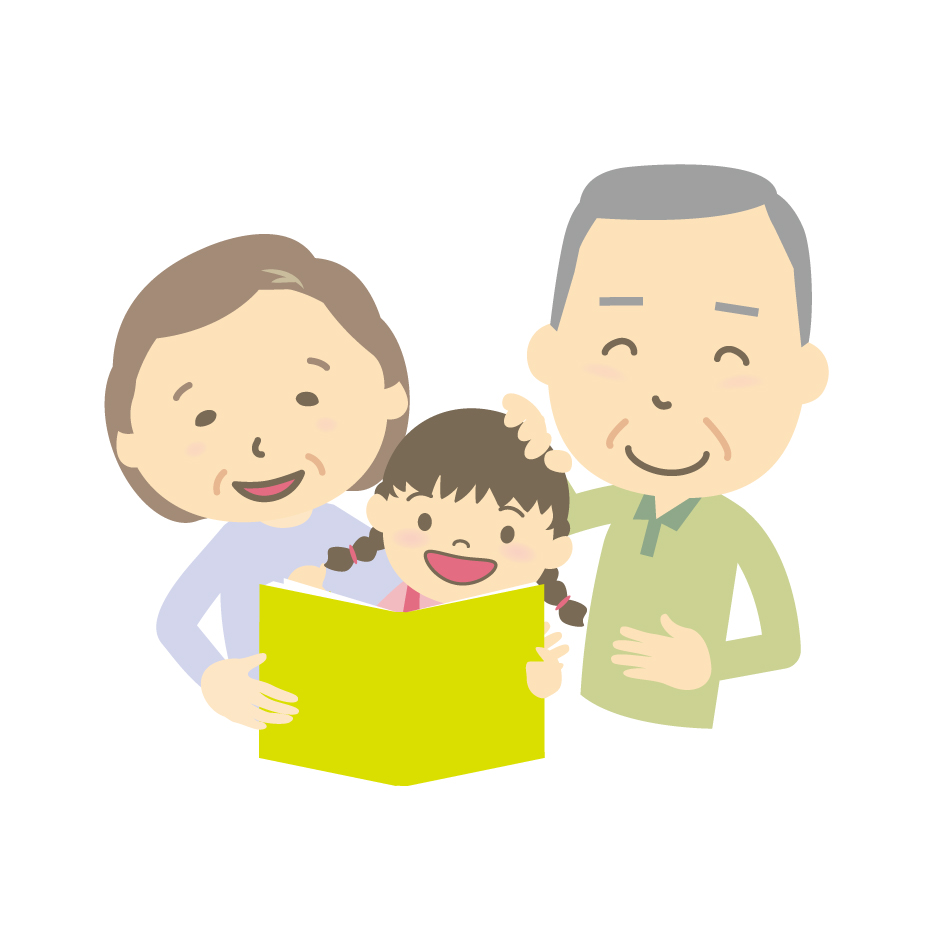こんな時、救急車を呼んでもいいの?判断に迷った時の対処法

出典:写真AC
急なケガや体調不良になったとき、救急車を呼んでもいいか迷った時はありませんか?
救急車や救急隊員の数は限られているので、症状が軽い場合は救急要請を控えた方が望ましいのですが、その判断はとても難しいものです。
そんな時のために、救急車を呼んだほうが良いか、今すぐに病院に行ったほうが良いかなど、判断に迷ったときに用いる電話相談窓口「救急安心センター事業(#7119)」「子ども医療電話相談事業(#8000)」をご紹介します。
救急安心センター事業 #7119について
救急安心センター事業では、看護師等の資格を持つ相談員が対応し、病気やケガの症状を把握して、緊急性や救急車要請の要否についてのアドバイスがもらえる電話相談窓口です。
緊急性が高い場合には、119番に電話を転送するなどして、救急車の要請を支援してくれます。
そのほか、診察が可能な医療機関の電話番号を教えてくれる医療機関案内や症状に応じた応急手当について助言をしてくれます。
2024年11月現在、#7119を設置しているのは全国で36地域となっており対象外となる地域もありますが、消防庁では「日本全国どこにいても#7119が繋がる体制」の実現を目指しており、全国での展開を推進しています。
対象外の地域の場合は、かかりつけの病院や最寄りの病院に相談、もしくは地方自治体に相談窓口が設置されているかを事前に把握しておきましょう。
※相談料は無料ですが、通話料は利用者の負担になります。
子ども医療電話相談事業 #8000について
子ども医療電話相談事業では、休日・夜間のこどもの症状にどのように対処したら良いのか、病院を受診した方が良いのかなど判断に迷った時に小児科医師・看護師に電話で相談できる電話相談窓口です。
こちらは47の都道府県すべてで実施しており、お盆や年末年始などにも利用できるので、小さなお子さまをお持ちの方にはぜひ覚えておいていただきたい窓口です。
発熱、頭をぶつけた、嘔吐、けいれんなど・・・救急車を呼ぶか迷った時はまずは相談してみましょう。
※相談料は無料ですが、通話料は利用者の負担になります。
救急車を呼んだ時に準備すること
救急車を呼んだ際に、電話口で応急手当などが必要な場合もあるので、落ち着いて指示に従いましょう。
そして、救急車が到着するまでに以下のような持ち物を準備しておきます。
<持ち物>
・保健証(マイナンバーカード)、診察券
・おくすり手帳、常用している薬
・現金 など
(乳幼児の場合)
・母子健康手帳
・紙おむつ
・哺乳瓶
・タオル など
救急車は、住所などの情報をもとに現場に向かっていますが、道路状況に詳しいとは限りません。
現場に複数人いる際は、救急車のサイレンが聞こえたら、現場の外に人を出して案内するようにしましょう。
まとめ
意識がない、もうろうとしているといった意識障害、大量出血、広範囲のやけど、顔や体の一部がしびれているといった場合は、すぐに救急車を呼ぶ必要があります。
ご家族であれば明らかにいつもと違う・様子がおかしい場合は、すぐに救急車を手配しましょう。
地域の救急相談窓口や救急病院などの問合せ先を確認し、電話機の近くに電話番号のメモを貼ったり、スマートフォーンや携帯電話の電話帳に救急相談窓口の電話番号を登録しておきましょう。
【参考】
政府広報オンライン「もしものときの救急車の利用法 どんな場合に、どう呼べばいいの?」
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201609/1.html
更新日:2024年12月27日
「みんなのシルバーひろば」では皆さんのご意見・ご要望をお待ちしております!
ご意見・ご要望は、以下の「銀のたまご意見箱」よりお送り頂けます。
「あれが気になる」「これについて教えて」など、どんな事でも構いませんので是非お声を聞かせて下さい!
 シルバーギア
シルバーギア