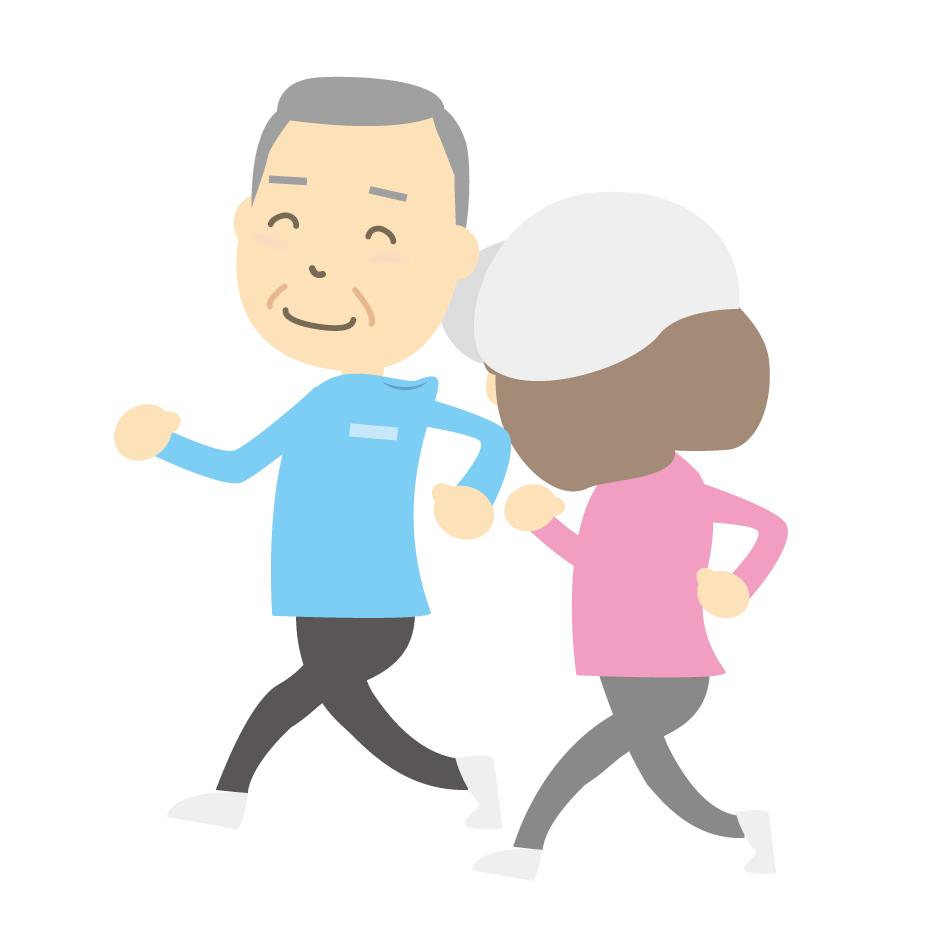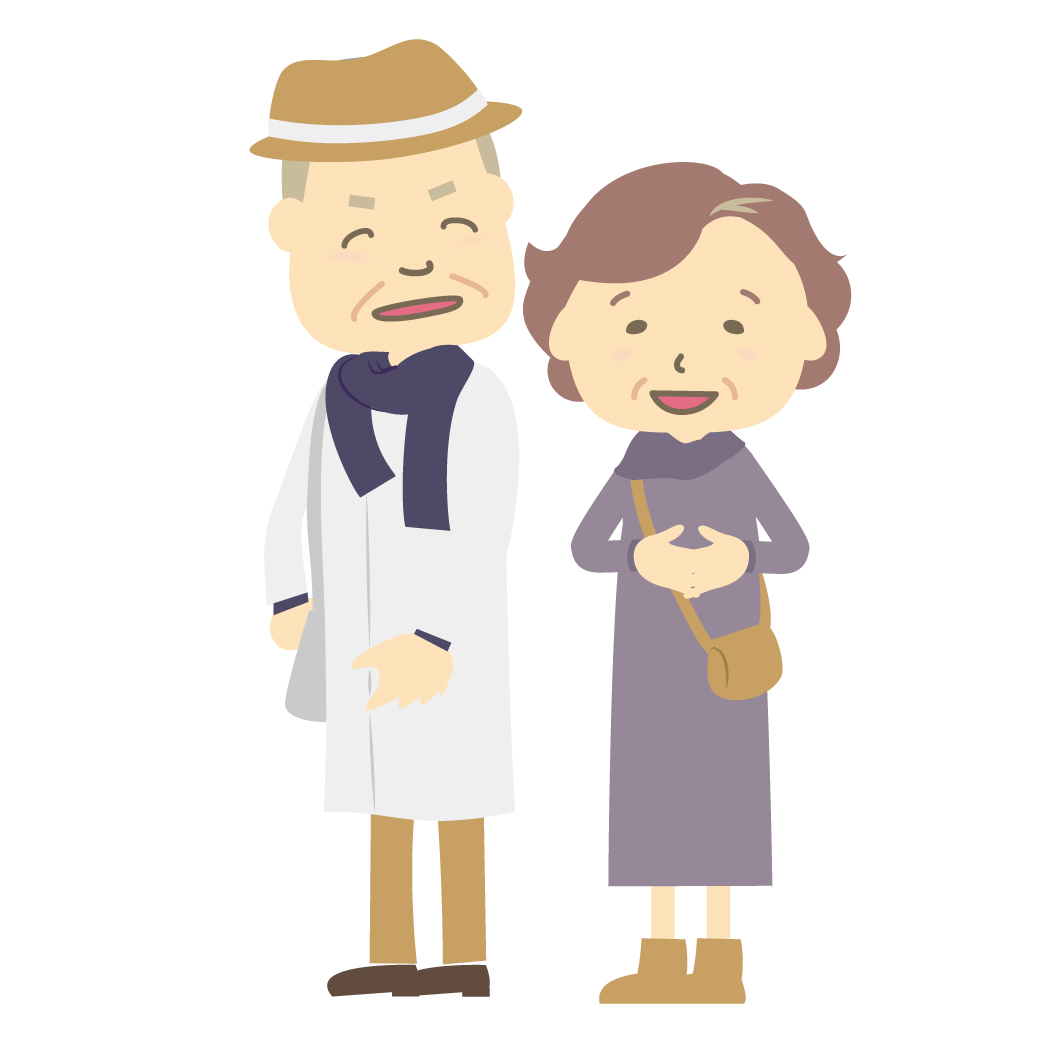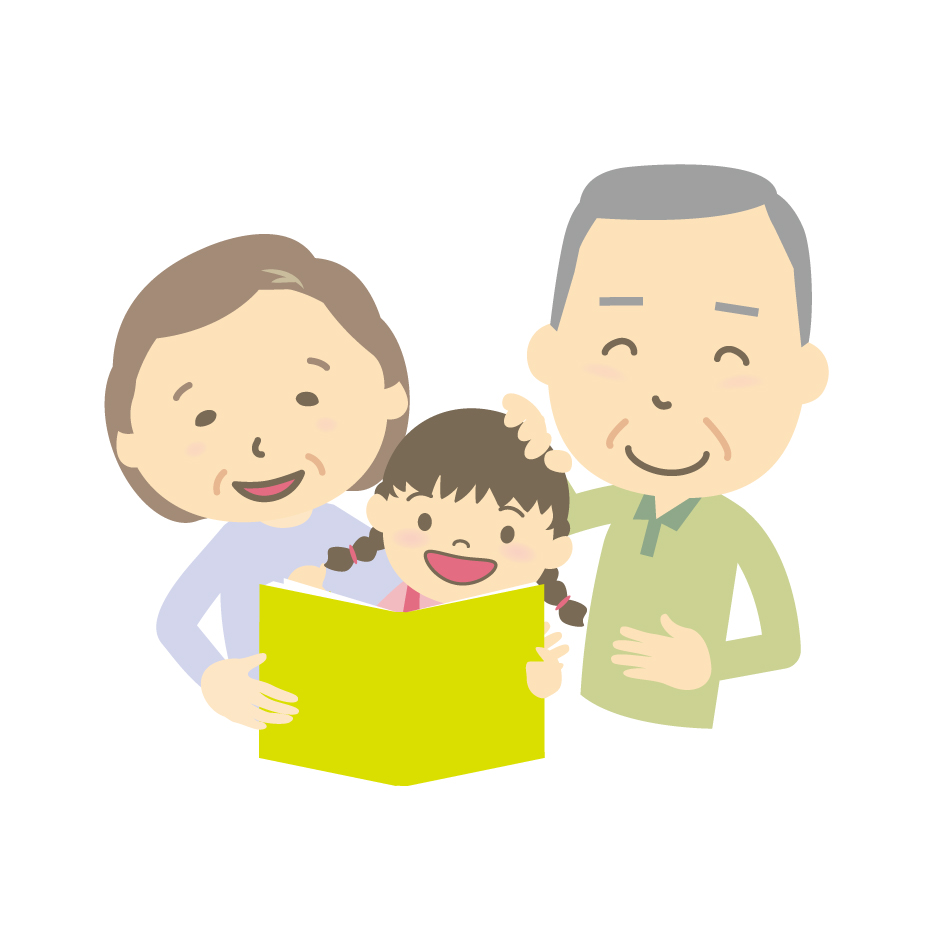生前贈与/非課税で行う為の6つの方法

出典:イラストAC
“非課税”という優しさを添えて贈る
生前贈与とは、亡くなる前に、自分の財産を他の人に無償で渡すことです。相続とは異なり、贈与する相手やタイミングを自由に選ぶことができます。生きているうちに先に財産を譲るものであるため、相続税ではなく贈与税がかかります。贈与税は財産をもらった時にかかり、もらった人が税金を払います。
「生きているうちに大切な人へ贈りたいけれど、贈与税が気になる...」 そんな思いに応える制度が、実はいくつも用意されています。条件を満たせば税金がかからないケースも。
ここでは6つの「非課税で贈与できる方法」をご紹介します。
非課税で贈与できる方法6選
1.暦年贈与の基礎控除
暦年贈与とは、1年間に受けた贈与に対して、年間110万円までなら贈与税が非課税になる制度です。
<注意点>
贈与者の死亡前7年以内(※)の贈与は、原則として生前贈与が無効で、相続税の算定対象となります。
※2023年12月31日までは「死亡日以前3年間」でしたが、2024年1月1日以降は「死亡日以前7年間」に変更されています。
2.相続時精算課税制度の特例
60歳以上の父母か祖父母から18歳以上の子どもか孫への贈与は、2,500万円(現金・不動産など)までなら非課税となります。2,500万円を超える場合、一律20%の税金がかかります。尚、相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が適用されます。
<注意点>
・相続時には贈与分も相続資産として計算され、相続税の対象となります。つまり、財産の相続だけを生前に行い、将来の相続時にまとめて課税されます。相続財産が基礎控除内であれば、贈与された財産も課税されず節税効果が高いです。
・相続時精算課税制度を利用すると、以降は暦年贈与を利用できません。
3.住宅取得資金贈与の特例
父母や祖父母から、マイホームの新築・取得や増改築等のための資金を贈与されたとき、最大で1,000万円まで贈与税が非課税になる制度です。
<注意点>
・適用期限:令和8年(2026年)12月31日まで
・非課税限度額は住宅の形態により異なります。(省エネ等の住宅用家屋:1,000万円/左記以外の住宅用家屋:500万)
4.夫婦間贈与の特例(贈与税の配偶者控除)
配偶者に対して「居住用の不動産あるいはその購入資金」を贈与した場合、2,000万円までが非課税になります。 贈与税の基礎控除額110万円を併せて使うこともできるので、2,110万円までが非課税になります。
<注意点>
・婚姻期間が20年を越える夫婦が対象です。同じ相手には一生に一度しか利用できず、贈与を受けた家や土地に住み続ける見込みであることが必要です。
5.教育資金贈与の特例
30歳未満の子どもや孫に対する教育資金の贈与は、1,500万円までなら非課税とされます。適応されるのは、学校などに支払われる入学金・授業料・給食費などです。それ以外の、学習塾や習い事にかかる費用に対する贈与は500万円までが非課税となります。贈与者は信託銀行などの教育資金口座に資金を預け入れ、金融機関が教育費の支払いを確認できた場合に(領収書等での用途証明)、受贈者の専用口座に入金される仕組みです。受贈者の普通預金などに一括で資金が振り込まれるわけではなく、後払い方式で入金されます。
<注意点>
・適用期限:令和8年(2026年)3月31日まで。
・贈与を受けた人が30歳になると、未使用分は課税対象になります。
6.結婚・子育て資金贈与の特例
親や祖父母から、18歳から49歳までの子どもや孫の結婚・子育て資金について贈与する場合、1,000万円(結婚資金は300万円)までが非課税となります。結婚資金として該当するものは、結婚式や結婚に伴う引越しなどにかかる費用です。子育て資金として該当するものは、妊娠・出産・不妊治療にかかる費用と、子どもの医療・保育にかかる費用です。贈与者は専用口座へ入金し、受贈者が引き出す為には領収書等での用途証明が必要です。
<注意点>
・適用期限:令和9年(2027年)3月31日まで。
・結婚・子育て資金の一括贈与契約は、受贈者が50歳になると終了し、その時点で口座に残っている金額に対しては、贈与税が課税されます。
・契約中に贈与者が亡くなってしまった場合、残された資金は相続税の課税対象となります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
上記6つの方法それぞれの注意点をみると、生前贈与は早い段階から計画的に行うことが重要と言えるでしょう。
また申請や手続きが必要なことに加え、教育資金贈与や結婚・子育て資金贈与は、金融機関での契約・管理が条件で、なかなかハードルが高く感じます。
そして一部の制度は、法改正により利用可能期間が変動するため、タイミングが重要です。
「うちの場合はどの制度が使えるの?」と思ったら、まずは銀行や税理士事務所のウェブサイトなどにある「生前贈与診断チャート」や「生前贈与シミュレーション」で確認することをオススメします。診断結果により、必要に応じて税理士・司法書士など専門家のアドバイスを活用してみてください。
【参考・出典】
国税局Webサイト
1.No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税):
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
2.No.4103 相続時精算課税の選択:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
3.No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
4.No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm
5.No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4510.htm
6.No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4511.htm
更新日:2025年7月11日
「みんなのシルバーひろば」では皆さんのご意見・ご要望をお待ちしております!
ご意見・ご要望は、以下の「銀のたまご意見箱」よりお送り頂けます。
「あれが気になる」「これについて教えて」など、どんな事でも構いませんので是非お声を聞かせて下さい!
 シルバーギア
シルバーギア